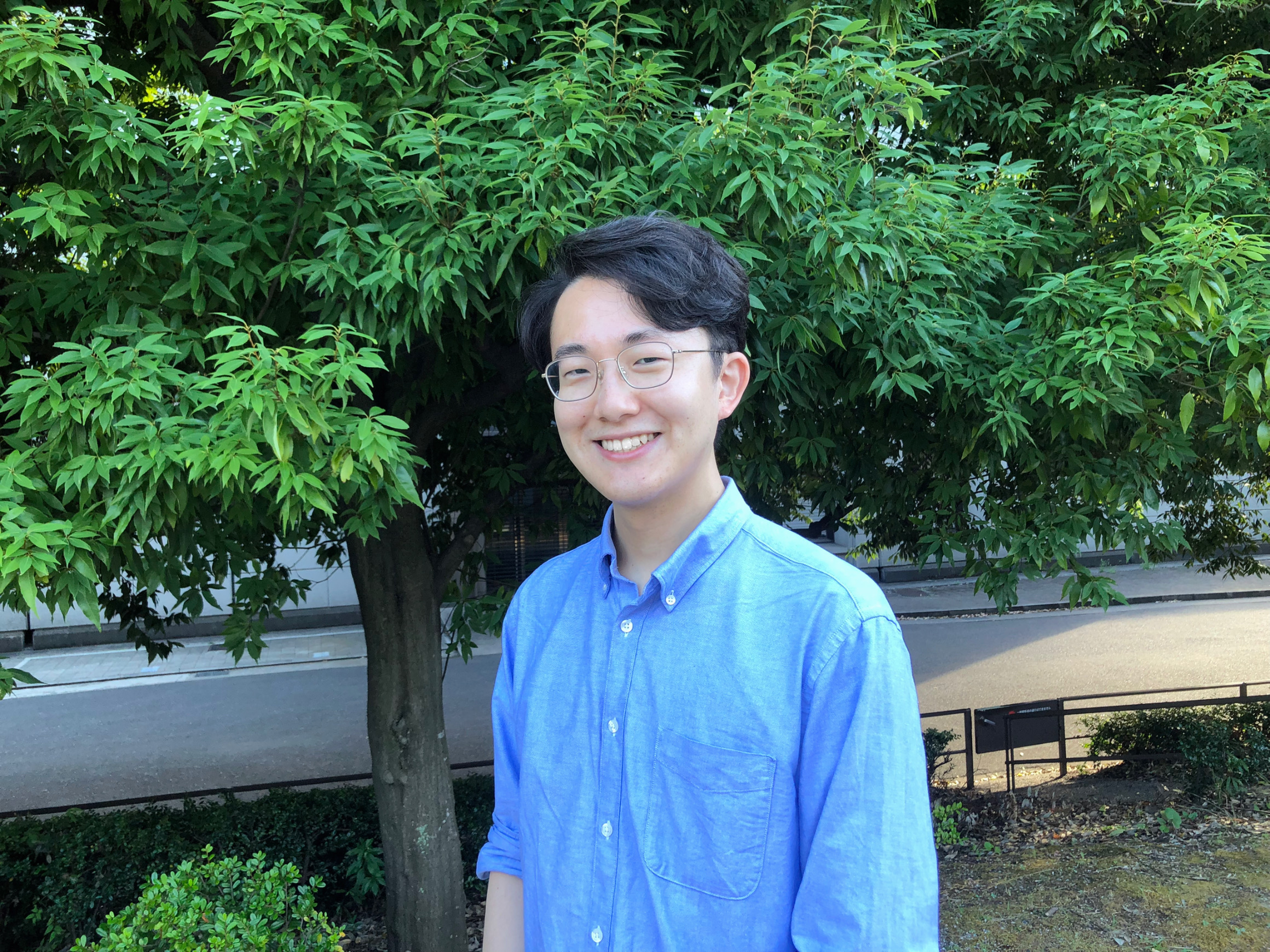「東南アジアの都市居住」第15回定例研究会
報告者:吉田 航太 (静岡県立大学 助教)
タイトル:「都市環境問題と「社会」の創造:インドネシア・スラバヤ市における住民参加型の環境運動の展開
言語:日本語
要旨:
本発表では、今年出版した『ゴミが作りだす社会――現代インドネシアの廃棄物処理の民族誌』の内容をもとに、インドネシアにおける都市の環境問題と地域社会の相互関係について論じる。1980年代以降のインドネシアでは、環境という問題設定を中心として、政府から自律した「社会(=地域住民)」を重視する理念が広まり、1998年の民主化以降は行政も後押しする形で参加型の開発プログラムが展開してきた。第二の都市スラバヤではゴミ問題が大きな課題となり、環境NGOなどが支援する形で住民参加型の廃棄物処理の取り組みが始まり、さらに市政府主催の環境コンテストによってこの動きは市全体へと広がっていった。興味深いことに、ここでの「住民」は、権威主義的なスハルト体制下で整備された組織を、権利の主体として読み替えることで成立している。様々な住民参加の技術・技法によって、もともとは上からの統制を目的とした制度が、環境運動を糸口として人々が新たに「住民」として「社会」を創造する回路となり、さらに新たな環境運動・政策の基盤ともなっているのである。しかし、こうした「社会」の創造は、草の根の民主化とも言える一方で、少数者を通じた人々の動員という側面も維持されており、また、別の形の社会の創造を妨げてもいる。そうした現在のインドネシアにおける環境問題と「社会」との複雑な関係を本発表では検討する。
略歴:
吉田 航太(よしだ こうた)
静岡県立大学国際関係学研究科助教。1990年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、博士(学術)。専門は文化人類学、科学技術社会論、東南アジア地域研究。主な論文に「ダークインフラの合理性――インドネシアの廃棄物最終処分場における不可視への動員とその効果」『文化人類学研究』22巻、「インフラストラクチャー/バウンダリーオブジェクトにおける象徴的価値の問題――インドネシアにおける廃棄物堆肥化技術をめぐって」『文化人類学』83巻3号、著作に『ゴミが作りだす社会――現代インドネシアの廃棄物処理の民族誌』(東京大学出版会)などがある。